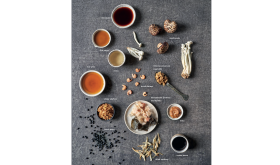日本初の海外資本によるワイン事業投資について。 Japan wine – some favourites(日本ワインのお気に入り)も参照のこと。この記事のショート・バージョンはフィナンシャル・タイムズにも掲載されている。
ブルゴーニュの有名生産者エティエンヌ・ド・モンティーユは、ピュリニー・モンラッシェのシャトーだけでなく、ムルソーには訪問客が引きも切らないワイナリーを、コート・ドールの名だたるアペレーションには37haもの羨ましいほど広いブドウ畑を所有している。
ところが2017年、彼がチームと共にそのこだわりを追求する場として翼を広げたのは、ブルゴーニュのドメーヌとしては異例の2つの「大陸」だった。1つはカリフォルニア南部、サンタ・バーバラに立ち上げたラシーヌ、そしてもう1つのエキゾチックな選択は日本最北端の大きな島、スキーで有名な北海道だった。上の写真は彼のまだ若い畑、下の写真は日本人同僚との1コマだ。
これはヨーロッパ人として、相当な信念に基づかねばできない選択だ。カリフォルニアでのワイン用ブドウ栽培には、ある意味長く輝かしい歴史がある。しかし日本でのそれはまだかなり難しいと言わざるを得ない。気候も地勢もブドウの樹に適しているとはお世辞にも言えないし、夏の降雨量は理想的な量をはるかに上回るからだ。
6月から10月までの断続的なモンスーン(訳注:に由来する降雨)はブドウの樹がかかりやすいカビ病を助長する。ブドウ栽培者たちは、腐敗やベト病からブドウを守るため、ありとあらゆる特殊策を講じなければならないが、その中には最もコストがかかる一方で「映える」手法も含まれる。日本の高級生食用ブドウ生産者に倣い、個々の房に小さな傘をかける手法のことだ。
大半のブドウの仕立て方は頭上に広がるパーゴラ(訳注:棚)で、ガリシア同様に雨からブドウを守る役割を果たすものの、その収量は途方もなく多い。一方で、最高品質のブドウの多くは風味を最大限に引き出すため収量を制限し、垣根仕立てで栽培されている。
日本にはブドウ畑にできる土地がほんのわずかしかない。新幹線から日本の田園風景を眺めたことのある人なら、日本の密度は何もかもが高いことをご存じだろう。大半のワイン生産者は年間生産量が数千ケースという超小規模で、そのブドウは小さな借地で栽培されていることがほとんどだ。
これらを鑑みれば、日本でワイン造りがこれほど盛んなのは特異な状況と言えるだろう。なにしろ生産者の数はここ10年でおよそ2倍の約500軒となったのだ。
日本の四季の変化は非常に明確で、生育期は比較的短い。冬が厳しいため、萌芽はヨーロッパよりずっと遅い5月、開花は6月末になることがある。また11月に雪が降るような地域ではそれまでに収穫を終えなくてはならない。
温暖な南部は一般的に雨が多すぎてブドウの成熟には適さない。そのため主要なブドウ栽培地は日本の北寄りに位置する: 東京のすぐ西にある山梨県、山梨県の西に位置し、標高の高さによるメリットを享受する長野県、そして最も北に位置し、最大の都道府県でもある島、北海道である。
ド・モンティーユが日本に興味を持ったのは2015年の来日時のことだった。「我々のように確立されたワイン産地で当たり前のように使われているあらゆる資材の入手が限られていて、気候面でもこの上ない逆境にもかかわらずブドウを栽培し、誠実にワインを造るための努力を惜しまない日本のワイン生産者たちのしなやかさ、強い意志、そして謙虚さに感動しました。彼らから海外のワイン生産者が日本に来てブドウ畑を作り、知識や経験を共有し、架け橋になってくれれば助かるのに、と言われたことも覚えています」。彼は現在函館に15haのピノ・ノワールとシャルドネの畑とワイナリーを所有、2023年にはわずかながらも初めての収穫を得た。「北海道は、私が他では味わったことのない、美しくて香り高く、エレガントで優美な、余韻に独特のうま味を感じるようなワインを生み出す地になると考えています。」そう彼はメールに書いている。
下の写真は彼が北海道に建てた真新しいワイナリーだ。
ド・モンティーユをはじめ、今のところ北海道のブドウ畑のほとんどは島の南部にあるが、北海道には可能性と入手性を兼ね備えた土地が本州よりも多く存在する。
ところで1つ興味深かったのは、日本で栽培されたブドウから造られたワインを「日本ワイン」、その5倍近い量が日本で販売されており輸入ワインや濃縮ブドウ果汁から造られたワインを「国内製造ワイン」と区別している点だ。この詳細はJapan wine – past and future(日本ワイン、その過去と未来)を参照してほしい。
日本の気候は湿度が高いため、生産者の間ではカビ病に耐性の高いハイブリッド品種の人気も高い。群を抜いて最も有名な赤ワイン用品種はマスカット・ベーリーAという、愛嬌もありつつ風変わりな名前の品種だ。この品種は日本で生み出された日本が誇るハイブリッドで、イチゴのような香りのする、魅力的でフルーティーなワインを生み出す。
ただし、日本では赤ワイン用品種より白ワイン用品種の方が多く栽培されている。ナイアガラやデラウェアのように果皮の色が薄いアメリカ系ハイブリッドも広く栽培されているが、白ワイン用品種として最も圧倒的な人気を誇るのは、ピンク色の果皮を持つ日本の甲州である。生食用にも用いられる品種だが、このヨーロッパのヴィティス・ヴィニフェラと中国系山ブドウの交配種が数世紀前にどのようにして日本に持ち込まれたのかは、今のところわかっていない。
甲州からは比較的ニュートラルで洗練された辛口の白ワインが多く作られており、私としては同じような純粋さを持つ刺身と特に相性が良いと思う。ただし、1ヘクタールあたり20トンを超える収量を大幅に削減することでワインの風味を高めようとする動きがあり、実際にそれを達成している畑もあるようだ。
先の訪日では、できるだけ多くの厳選された日本ワインを試飲できるよう、何人かの関係者にお願いしておいた。圧倒的に素晴らしかった2本の白は山梨の98Winesの甲州で、私の経験では初めて、最高品質の甲州は熟成可能であることを証明してくれたワインだ。1本は2022、もうひとつは2019だった。ワインメーカーの平山繁之氏は、日本の数少ない大手ワイン企業であり、キリン傘下のシャトー・メルシャンで長年醸造責任者を務めていた人物だが、独立後はビール醸造と、この洗練されたワイン醸造の両方を一人で担っている。
もうひとつ印象に残った白ワインは、セイズファームの田向俊氏が造る、樹齢8年のブドウから造られた、ある意味納得の品種アルバリーニョだ。田向氏の見た目は純なヒップスターといったところだが、(日本のビジネスでは必須の)名刺には「執行部役員、ワイン製造部部長、栽培醸造責任者」と書かれていた。このガリシアのアルバリーニョは果皮が厚く雨に強いため、複数の日本ワイン生産者に選ばれているようだ。2022と2023のヴィンテージ、どちらも楽しむことができた。
ところが驚いたことに、ワイン・ライターの猪瀬聖氏とワイン業界のベテラン石井もと子氏が共同で企画したテイスティングでは、どちらかといえば白ワインよりも赤ワインに軍配が上がった。
マスカット・ベーリー・Aは、長期熟成には向かないものの総じてとてもチャーミングだった。それに続いてテイスティングしたのは北海道のピノ・ノワール3種だ。買いブドウから造られたド・モンティーユの2020、繊細というよりは独創的なドメーヌ・タカヒコ、そして山梨にある中央葡萄酒の三澤一族が比較的最近北海道に設立した千歳ワイナリーのものだ。
だが私が出合った赤ワインの中で、むやみに個性を追求してはいないものの最も野心的だったのが、日本で数少ない大手ワイン企業の1つ、マンズワインのボルドー・ブレンド2021だった。山梨大学で学び、ボルドーとブルゴーニュで修業を積んだ西畑徹平氏が造るワインだ。彼は長野県でカベルネ・ソーヴィニヨンとメルローの完熟に成功している。赤ワインは今や日本でもアルコール度数14%に達するのだ。
東京で開催されたテイスティングの際、彼はマンズのトップ・キュヴェにつけられたブランド名「ソラリス」が、北ヨーロッパで人気が高まっている白ワイン用ハイブリッド品種と同じなので混同されないかと心配していた。明らかに国際的な視野と経験を備えている彼に、私は後日メールで日本とヨーロッパのワイン造りの主な違いは何かと尋ねてみた。
「日本でのワイン造りの難しさは、基準がないことです。」そして彼は続けた。「どのブドウ品種がどの地域に最も適しているのか、まだわかっていません。また収量に制限がなく、その見極めも困難です」。彼はさらに専門的な栽培・醸造用設備の不足を訴え、ブドウ苗の価格がフランスの10倍もすることを指摘した。「それでも私は日本の多様な気候を否定的に考えてはいません。」そしてこう付け加えた。「なぜならそれがワインに個性を与えてくれるからです。まだまだ、どんな挑戦でもしていきますよ!」
お薦めの日本ワイン
私が20点満点中16.5点以上をつけたワインは以下の通り。
白ワイン
98WINEs、 穀 甲州 2019 山梨 10.5%
勝沼醸造、 アルガブランカ ブリリャンテ 甲州 2017 山梨 12%
セイズファーム、 プライベートリザーヴ アルバリーニョ 2023 富山 12.8%
セイズファーム、 プライベートリザーヴ アルバリーニョ 2022 富山 13.2%
ド・モンティーユ&北海道 ケルナー2022 北海道 12.5%
モンガク谷ワイナリー、 杤 2018 北海道 12.5%
赤ワイン
千歳ワイナリー、 北ワイン ピノ・ノワール プライベートリザーブ 2021 北海道 13%
ド・モンティーユ&北海道 ピノ・ノワール 2020 北海道 12.5%
ドメーヌ・タカヒコ、 ナナツモリ ピノ・ノワール 2021 北海道 13%
シャトー・メルシャン、 椀子シラー プレミアム2021 長野 12.5%
マンズワイン小諸ワイナリー、 ソラリス ラ・クロワ2021 長野 14%
丸藤葡萄酒工業、ルバイヤート プティ・ヴェルド2014 山梨 12.5%
ベルウッドヴィンヤード、 コレクション スペリオール マスカット・ベーリーA 2023 山形 12%
シャトー・メルシャン マスカット・ベーリーA 2020 山梨 13%
ダイヤモンド酒造、 シャンテ Y.A Huit マスカット・ベーリーA 2018 山梨 13%
テイスティング・ノート、スコア、お勧めの飲み頃については、 Japan wine – some favourites(日本ワインのお気に入り)を参照のこと。日本ワインはわずか0.02%しか輸出されていないため、本記事で紹介できる海外の取扱業者はない。
jancisrobinson.com限定日本語版(翻訳・小原陽子)